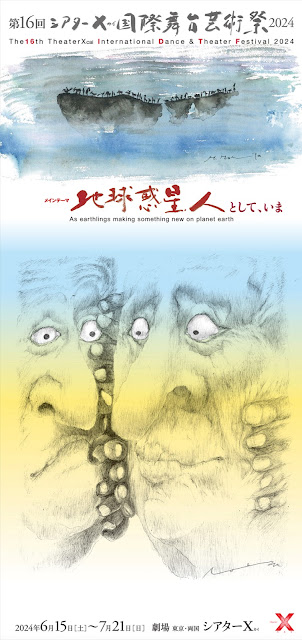深谷正子 ダンスの犬 ALL IS FULL:
動体観察 2daysシリーズ[第3回]
■
極私的ダンスシリーズ
深谷正子『庭で穴を掘る』
日時:2024年7月22日(月)
開場: 6:30p.m.、開演: 6:00p.m.
ゲストダンサーシリーズ
『男性3人によるインプロビゼーション』
出演: 伊藤壮太郎、津田犬太郎、◯ヰ△(マルイサンカク)
日時:2024年6月23日(火)
開場: 6:30p.m.、開演: 7:00p.m.
会場: 六本木ストライプハウスギャラリー・スペースD
(東京都港区六本木5-10-33)
料金/各日: ¥3,500、両日: ¥5,000
照明: 玉内公一
音響: サエグサユキオ
舞台監督: 津田犬太郎
会場受付: 玉内集子、曽我類子、友井川由衣
写真提供: 平尾秀明
問合せ: 090-1661-8045
パフォーマーのリクエストにより、照明や音響のスタッフを不要とした公演の前半、暗転のなか黒い服装をしていた伊藤壮太郎、◯ヰ△のふたりは、闇夜のカラス状態でなにをしていたのか肉眼でよくわからず、まさしく事態は闇鍋状態で進行していった。事態を把握するため、観客もまずは暗闇に目を慣らす時間が必要だったように思う。黒幕が張られた楽屋裏から引き出した脚立に乗って、天井の長押から紐に結んだ石を吊りさげる◯ヰ△、リュックを背負い自然光が入るホリゾント窓の前で影になって動く伊藤壮太郎、白いガウンのような裾長の服を着て、すわったり立ったり幽霊のようにゆらめく津田犬太郎、公演冒頭からかなりの時間、3人がどんな関係を結ぼうとしているのか見当すらつかない状態が延々とつづいた。
一般に表現者が「即興」にたどり着くにはさまざまな理由があるだろうが、ここで「男性3人によるインプロビゼーション」というのは、演出のためのスタッフを置かず、可能なかぎり他者の介入を排することを意味している。即興することは、自由や偶然性を徹底することだったり、完璧な自己表現の実現であったり、即興ダンスを踊ることだったりとさまざまだが、本公演で目指されたのはおそらくもっと単純なこと、振付の不在であり、演出家の不在であり、リハーサルの拒否だったように思う。換言すれば、劇場の拒否、劇場というシステムを支えるものすべての拒否ということになるだろうか。この点において、2daysシリーズを主催する深谷正子が伊藤壮太郎と知り合ったのが、タップダンスの米澤一平が“場づくり師”として登戸の高架下で主催していた「ノボリトリート」であったことは、本公演を理解するうえで重要だろう。
2days公演の初日におこなわれる深谷正子の極私的ダンスは、スペースDを完全暗転のできる虚構空間にすることでシリーズ前史としてある七針でのそれと差異化を図る方向でおこなわれている。それに対して、2days公演の2日目を構成したゲストダンサーシリーズの「男性3人によるインプロビゼーション」のありようは、むしろ先月おこなわれた女性3人による『月の下の因数分解』に近く、群舞として初共演したメンバーが、劇場の拒否をより徹底したパフォーマンスといえる。両者をくらべてみるとき、上手・下手・ホリゾントにあたる壁についている窓に戸を立てることなく自然光を入れ、どちらの公演にもダンサーが窓を開放する場面があった点に注目したい。男性3人のセッションはこの方向をさらに敷衍して、ギャラリー階段の扉口から光をいれたり、扉を開放状態にしたり、黒幕のおりた楽屋からも出入りすることでスペースDの空間にいくつもの穴を開け、実際にさかんな出入りをおこなうことで劇場空間をストリートに変えていた。出会いを語るならば、スペースDをノボリトリートの高架下に変えたといういいかたも許されるだろう。スペースDの劇場性は、暗転下の自然光だけでおこなわれた前半から、白い衣装から黒い衣装に着替えた津田犬太郎が小さな照明器具を持ちこんだり、大きなPAを背負って雑踏する音やコントラバスの響きを出しながらステージを左回りで歩行していく後半、わずかに回復した。こうした津田のパフォーマンスこそは、不在の演出家を代行するような意図をもって、この日の公演のストリート性を深谷の意図する劇場性につなげるものだったといえるだろう。このことは公演後におこなわれた各人のインタヴューで、津田が「なによりも終わりがあってよかった」と述べたところにもあらわれている。
初回の小松亨ソロは未見なのだが、2回目以降、群舞を再定義するように進行しているゲストダンサーシリーズは、ダンスにおける作品性の外に出て、もしくはダンスの作品性とダンサーの身体性の境界線上で起こっていることを意識化するようにしておこなわれている。深谷のいう「動体観察」とは「それぞれの方法で穴を掘り続けている表現者」の「身体の魅力」にフォーカスするための公演形式の模索であるが、その背景には、劇場をひとつの表象システムにしているものへの批判が存在する。「動体観察」とは現代における身体のリアルの再獲得を目指すものだろうが、そのことはかならずしも劇場に「外」があるということにならないように思う。ダンス公演をめぐるこうした複雑な連立方程式をひとつずつ解いていくところに、「動体観察」の成否もかかっているのではないだろうか。(北里義之)■
深谷正子 ダンスの犬 ALL IS FULL:
動体観察 2daysシリーズ