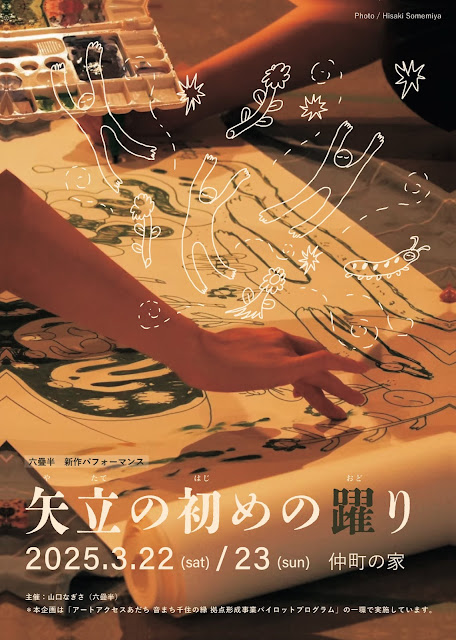『ANTIPIOL アンティピオル』
王子神谷 シアターバビロンの流れのほとりにて
■
アンティピオルさんのテーマ
ママの 林檎が 食べたい
手が 猫のように 見える
それは 前触れ
もうじき アンテイピオルさんが やってくる
Je veux manger la pomme de maman
Tes mains ressemblent à celles d'un chat
C'est un signe avant-coureur
M.Antipiol viendra bientot
■
今回の公演タイトル「Antipiol(アンティピオル)」は、『分裂病の少女の手記』の本のなかで実際に病院で腫物に使われていた軟膏の名前。少女は精神疾患で入院中に聞こえた幻聴の声をアンティピオルさんと呼ぶ。嘲笑し命令する声のアンティピオルとの闘い。彼女だけでなく誰でも心の中にある自分でもわからない感情、押さえつけられた思い、トラウマなどが何かのきっかけでアンティピオルのように現れるものだと思います。
坂田有妃子(UNIca主宰)
■
出演・振付: 上田 創、古茂田梨乃、斎木穂乃香、
鄭 亜美、平田理恵子、坂田有妃子(演出・構成)
演奏: Miya(modular flute)、池田拓実(computer、他)
アフタトーク: 佐々木誠(28日)
藤本俊行、侘美秀俊(29日マチネ)
日時:2025年3月28日(金)開演: 19:00
29日(土)開演: 14:00/開演: 18:00
30日(日)開演: 14:00
開場時間は開演の30分前
会場: シアターバビロンの流れのほとりにて
(東京都北区豊島7-26-19)
料金/一般/前売: ¥4,200、当日: ¥4,500
U29/前売: ¥3,500、当日: ¥3,800
高校生以下/前売: ¥1,000、当日: ¥1,300
シニア割・障害者割/前売: ¥4,000、当日: ¥4,000
リピーター割: ¥4,000
UNIca応援チケット: ¥6,000
来られないけど応援チケット: ¥2,000
(後日映像配信をご覧いただけます。)
音楽・音響: 侘美秀俊
照明: 藤本俊行(Kinsei R&D)
衣装: るう(Rocca Works)
舞台監督: 原田拓巳
記録撮影: 松本和幸
記録映像: 粟屋武志
宣伝美術: 長谷川友紀
WEB: 中島侑輝
制作: 滝沢優子
舞台協力: 武田ゆり子
美術協力: サカタアキコ
協力: セキネトモコ、山村佑理、
Sophia Ellen Manami Crouzet
主催: UNIca
助成: 公益財団法人 東京都歴史文化財団
アーツカウンシル東京[東京都芸術文化創造発進助成]
■
ダンスアート制作団体「UNIca」のネーミングは、スペイン語で「唯一の、奇妙な、とっておきの」という意味に由来するというが、訳語の選択は、公演ごと作品ごとにリサーチをおこなうクリエーションスタイルや作品傾向についていったものらしく、言葉は同時に、「ただ一つの、ただひとりの、独自の、特有な」というややニュアンスを異にする意味も持ちあわせている。こちらは共通のカツラをかぶり共通の衣装を身につけた数人の女性ダンサーが、ミニマリズムをベースにした振付で一体となって踊る/動くという少女群舞のイメージに直結する訳語になるだろう。UNIcaの群舞は、個々の身体がユニゾンの動きによって連結されるのではなく、ソロのありようを排除して、最初から存在のワンネスを際立たせながらアメーバのように瞬間ごとに変異していく生物体として踊られている。すなわち、群れる少女は性的存在としてではなく、細胞レベルにまで下降した生命現象の位相で蠢くものを視覚化/感覚化する媒体としてとらえられ、それが作品の特異性をも構成しているのである。そのような群舞が、今回の作品『アンティピオル』では、主人公のルネにとって“声はすれども姿は見えず”という「アンティピオル」の幻聴を舞台に登場させるにあたり、上田 創による男性的実体──上田の演技は、サイレント映画の吸血鬼ノスフェラトゥを連想させるもの(人形めいた悪魔)だった──が与えられることで、ルネの統合失調症という出来事に、男女対立という性的レベルを持ちこむことになった。
作品のインスピレーション源となったM.セシュエー著『分裂病の少女の手記』(1955年11月、みすず書房)には、すぐれてユダヤ・キリスト教的な不全感からくる自己処罰の感情に責められるルネは登場しても、性的な衝動に悩まされるルネは登場していない。宗教的な原罪感情については、ルネ自身が聖書のエピソードを引用していることとか、彼女の経歴を記した「付録」のページに、「十一歳の頃、宗教に熱心になり、毎朝五時に起きてミサに出た。また墓地を熱心に見回りお墓の掃除をした。彼女は死者に話しかけ、墓の前の一部を、放置してあるお墓に供えるのを許してくださいといい、死者が承諾する声を聞いたように思った。」とあるなど、キリスト教圏特有の精神構造が背景をなしていることがわかる。この問題は、放っておけばほぼ自動的に学校組織や医療組織(精神病院)の問題に敷衍していくが、ダンス批評を大幅に逸脱してしまうことになるのでいまは控えることにしたい。上記の引用文でも「声」に触れられているが、絶えることなく命令してくる「組織」の長官「アンティピオル」も含め、物語に登場する精神分析医のママ、小さな猿、お人形のエゼキエルなど様々なキャラクターは、現実を構成する意味を失う一方、理由もなしに到来する裸の言語とともに経験されている。『分裂病の少女の手記』は、ルネ自身による物語とセシュエーによる精神分析のテキストから構成されているのだが、あえて言語体験を軸にしていえば、第二部の「解釈」の章は、統合失調症の「理由もなく」を前にして、フロイトをはじめとする精神分析の言語が(出来事に遅れて)セシュエーに到来してくる章(セシュエーの物語)と考えることもできるだろう。彼女が構成した著書において、物語の終わりは症状の治癒にではなく、出来事の再言語化に設定されているのである。
少女たちの群舞は、(観客には見えているが少女たちには見えていないらしい)アンティピオルの出現と消滅を境に、前半/中盤/後半で大きく性格を変える。前半の中心は、2人並んで双子のようなしぐさをするデュオ、背中あわせになる2人の足元をバックで抜けていく1人という組体操のようなトリオ、4人が床にすわった姿勢で重なり上体を回転させるのを残った1人が剥がしにくる群舞などが、全体でひとつのサイクルを描くように組みあわされ、ヴァリエーションとともに反復されていく場面で、ルネが学校の休憩時間に校庭で友達と遊ぶ場面を連想させるものだった。お手玉のようなたくさんのジャグリングのボールが床を伝って投げこまれるのと同時にアンティピオルが登場、ノスフェラトゥの怪人のようにステージを歩き回り、箱馬のうえに集まって震えている少女たちを、ひとり、またひとりと羽交い締めにして上手に運んでいくのが中盤の場面。運ばれた少女たちは木偶人形のように両手をあげて顔を伏せ、じっと動かなくなる。この中盤で特に印象的だったのは、静止する少女たちの腰や肩にボールを載せたアンティピオルが、観客席前に箱馬をひとつ出してすわると、まるで彫刻作品を鑑賞するようにして、自分がしたことの成果を満足気にながめたことである。作業を終えたアンティピオルはホリゾント前に集めた箱馬をベッドがわりにして横たわる。少女たちは動き出し、UNIcaのワンネスを取り戻したミニマルな群舞を展開していく。なかには植物の生態系を癒しに結びつける前公演の『菓』を引用する場面も登場した。生命の感覚を回復した少女たちは、箱馬のうえで寝こんでいるアンティピオルを取り囲み、上手のカーテン裏まで転がしていった。
身体の回復と現実への帰還をめぐる物語のあとにやってくるエピローグは、少女たちがステージに散らばり、思い思いにジャグリング・ボールに触れるような、触れないような場面で暗転となった。クリエーションの段階で、ジャグラー山村佑理のワークショップを受ける実践的リサーチが試みられたが、そのときの感想を、坂田がメンバーを代表してノートに記している。「実際にワークショップを受けてみて感じたのは、ボールに対しての自分の感覚をリセットして、広げていくことの大切さでした。」(『「Antipiol」を創る その③』)このテクストを勘案すると、エピローグにおけるジャグリングの場面は、生の喜びを伴うルネの現実への帰還がどういうものであったのか、その内実をダンサーたちの触覚を介して、ダイレクトに観客の身体に伝えようとする場面だったのではないだろうか。細かい指摘になるが、もう一点触れておかなくてはならないのは、少女たちが鼻歌のように口ずさむ歌である。歌詞ははっきりと聞き取れず、それがはたしてアンティピオルの歌であったかどうかはわからないままなのだが、回復過程の最後の階段を登るルネがリンゴを(乳のように)飲むという妄想の美しさともども、これが身体性や全体性を取り戻し、「組織」の命令をやめないアンティピオルの声を弾きかえすルネの闘いの歌(声)であったことは間違いないであろう。男性ダンサーの登場、ジャグリング・ボールの採用、物語性の導入と、いくつもの試みに開かれたシンUNIcaの作品において、とりわけて希望を感じさせる場面になっていた。■
(北里義之)